佐藤 嘉市|安曇野ゆかりの先人たち
記事ID:0052162 印刷用ページを表示する 掲載日:2025年1月27日更新
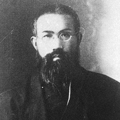
佐藤 嘉市
さとう かいち
常念岳を原点にすえた教育をした堀金小学校長。臼井吉見に大きな感化を与える。
| 生年月日 | 1877年(明治10) |
|---|---|
| 没年月日 | 1959年(昭和34) |
| 関連地域 | その他(飯山市。堀金小学校長を務め、常念岳を原点にすえた教育を行う。) |
| 職業・肩書 | 教育功労者 |
| 活躍年 | 大正時代 |
| ゆかりの分野 | 文化(教育) |
経歴
下高井郡高野村(現:飯山市)に生れました。長野師範学校を卒業して、下高井・下水内郡下に勤務しました。埴科郡で視学官をしていた時、聖山の頂上から常念岳を遠望し、その美しさに惹かれました。1916年(大正5)11月に、望まれて常念岳のふもとの堀金小学校に校長として着任します。このころ、安曇平で登山への関心が高まっていたことから、職員会に提案して常念研究会を発足させました。1917年(大正6)、常念岳調査のため、自ら三俣の上までの踏査を行います。8月には多くの村人の参加を得て、第1回の団体登山を行って大成功を収めました。1918年(大正7)、石室設置のために常念岳を調査し、夏休みには石室の建設と登山道の開拓を成し遂げました。
1919年(大正8)3月に堀金小学校を去るまでの3年間、常念岳を教育のよりどころとし、毎朝の朝会で「常念を見よ」と児童生徒に呼び掛けて、その美しさを讃え続けました。人々から「常念校長」と呼ばれ、自らも「常念山人」と称しています。
略歴譜
| 1877年(明治10)6月15日 | 下高井郡高野村関沢(現:飯山市)に、父新蔵と母幾(いく)の長男として生れる。 |
|---|---|
| 1884年(明治17)4月 | 高野学校関沢支校(十王堂)に入学する。 |
| 1888年(明治21)3月 | 豊郷学校高野支校を卒業する。 |
| 1889年(明治22)4月 | 下水内郡立下水内高等小学校(飯山町)に入学する。夏季は徒歩通学、冬季は真宗寺に下宿して通学する。 |
| 1890年(明治23)4月 | 下水内高等小学校第3学年に編入する。 |
| 1892年(明治25)3月 | 下水内高等小学校を卒業する。家居し小菅菩提院住職遠藤師につき、近古史談・日本政記・日本外史・四書五経等を学ぶ。 |
| 1892年(明治25)10月 | 小菅尋常小学校一時雇教員となる。 |
| 1893年(明治26)4月 | 小菅尋常小学校前坂分教場一時雇教員となる。 |
| 1894年(明治27)4月 | 飯山尋常小学校一時雇教員となる。 |
| 1895年(明治28)4月 | 長野県尋常師範学校に入学する。 |
| 1899年(明治32)3月26日 | 長野師範学校と校名を改称した最初の卒業生となる。 |
| 1899年(明治32)3月26日 | 組合立下高井高等小学校訓導となる。9年間在任し三回の卒業生を担当する。 |
| 1899年(明治32)7月13日 | 六週間現役兵として高崎聯隊に入隊し、国民軍幹部適任証を受領する。 |
| 1890年(明治33)8月 | 東北中央山脈を単身1か月かけて踏査し、那須・磐梯・岩手・岩木・鳥海山等に登る。 |
| 1891年(明治34)6月 | 丸山弁三郎氏と佐渡旅行をする。 |
| 1893年(明治36)5月 | 「下高井繁盛記」を編纂し出版する。 |
| 1895年(明治38)5月8日 | 下水内郡岡山村西大滝の斉藤寿一郎長女たいと結婚し中野市一本木に居をかまえる |
| 1898年(明治41)3月31日 | 下高井郡瑞穂尋常高等小学校訓導兼校長となる。 |
| 1902年(明治45)6月13日 | 下水内郡視学となる。 |
| 1915年(大正4)10月30日 | 埴科郡視学となる。 |
| 埴科郡で視学官をしていた時、聖山の頂上から常念岳を遠望し、その美しさにひかれる。 | |
| 1916年(大正5)11月20日 | 南安曇郡組合立堀金尋常高等小学校訓導兼校長となる。 |
| 1916年(大正5)12月9日 | 南安曇郡堀金農工補習学校長を兼務する。 |
| 常念岳を教育のよりどころとし、毎朝の朝会で「常念を見よ」と児童生徒に呼び掛けて、その美しさを讃える。 | |
| 1917年(大正6)7月 | 堀金小学校校内に常念岳研究会を発足させる。 |
| 1917年(大正6)8月10日 | 常念岳団体第一回登山をする。 |
| 1918年(大正7)6月27日 | 常念岳登山道・石室建設のため、村内に趣意書を配布して寄付を募る。 |
| 1918年(大正7)9月23日 | 堀金尋常高等小学校創立三拾周年記念に、学校沿革誌を編纂し村内に配布して学校への関心を高める。 |
| 1918年(大正7)11月27日 | 妻たい流行性感冒に罹患、肺炎を併発して常念寓にて死去する。 |
| 1919年(大正8) | 下高井郡瑞穂尋常高等小学校訓導兼校長兼瑞穂農工補習学校長として、再度郷里の校長となる。単独で樺太・北海道を一ヶ月にわたって視察する。 |
| 1920年(大正9)4月6日 | 先妻兄斉藤宗誠の仲介により、下水内郡常盤村上水沢の高橋米吉六女たかと結婚する。 |
| 下高井郡第四区職員研修会に、京大志田博士・神戸高商佐藤理学士等を招き研究会を進める。 | |
| 皇太子殿下御誕辰日を記念し、第四区職員児童生徒の毛無山登山を実施する。 | |
| 1922年(大正11)4月1日 | 下高井郡平岡尋常高等小学校訓導兼校長兼平岡実業補習学校長となる。 |
| 質実剛健を目標とし野球等を奨励する。 | |
| 蔵書50冊を寄附し有志の寄附を募って学校図書館を創設する。 | |
| 1923年(大正12)4月 | 下高井教育会副会長となる。 |
| 1924年(大正13)7月30日 | 下高井郡平隱尋常高等小学校訓導兼校長兼平隱実業補習学校長となる。 |
| 中央校舎・奉安殿・講堂・東校舎の新改築につとめる。 | |
| 岩菅登山・雪艇・運動競技を奨励する。 | |
| 果亭等の先覚の顕彰・学校沿革等を平隱教育に掲載し、村内に配布して学校教育への関心を高める。 | |
| 下高井教育会第二支会の事業として、西尾実・金原省吾・藤村作等の講師を聘し、山ノ内夏期大学を開く。 | |
| 1928年(昭和3)5月14日 | 朝鮮半島や満州を旅行。釜山・京城・奉天・新京・ハルピンを経て大連港より帰途に就く。帰郷後、下高井農学校で旅行の講演をする。 |
| 1928年(昭和3)6月26日 | 八ヶ岳に登る。 |
| 1928年(昭和3)12月15日 | 従七位に叙せられる。 |
| 1931年(昭和6)3月27日 | 善光寺温泉に春原青年会長と頭山満翁を訪ねる。 |
| 1931年(昭和6)4月 | 下高井教育会長となり、山ノ内夏期大学を開設する。 |
| 1932年(昭和7)3月14日 | 勲八等瑞宝章を授けられる。 |
| 1932年(昭和7)7月15日 | 正七位に叙せられ高等官六等を以って待遇せられる。 |
| 1934年(昭和9)4月3日 | 皇居二重橋前における全国小学校教員代表長野県副団長として、御親閲を受ける。 |
| 1934年(昭和9)11月8日 | 宮内大臣より新宿御苑観菊の御会に招待される。 |
| 1935年(昭和10)4月10日 | 勲七等瑞宝章を授けられる。 |
| 1935年(昭和10)10月10日 | 従六位に叙せられ高等官五等を以って待遇せられる。 |
| 1935年(昭和10)11月22日 | 台北市に開催の帝国教育会主催全国初等教育者大会に県代表として参加する。会終了後視察団長として全島を一周する。 |
| 1936年(昭和11)3月31日 | 下高井郡平隱青年学校長を兼務する。 |
| 1937年(昭和12)3月25日 | 門下山本義久による感恩碑除幕式を行なう。 |
| 1937年(昭和12)3月31日 | 依願退職する。 |
| 1937年(昭和12)4月 | 旧友丸山弁三郎の衆議院議員立候補につき応援演説をする。 |
| 木島小学校職員に11月まで伝習録の講義をする。 | |
| 1937年(昭和12)7月 | 象山神社建立資金募集に奔走する。 |
| 1940年(昭和15)7月15日 | 小菅神社における瑞穂青年会主催演武会第30回記念大会において、創立以来の功により感謝状並びに記念品を贈られる。 |
| 1940年(昭和15)10月10日 | 紀元2600年記念式典に内閣総理大臣近衛文麿より県民代表として招待される。 |
| 1941年(昭和16)7月 | 正受庵復興資金募集に尽力。保存会・下水内教育会より金一封を贈られる。 |
| 1943年(昭和18)6月20日 | 関東聯合教育会より教育功労者として教育功労賞を授けられる。 |
| 1943年(昭和18)11月1日 | 長野県方面委員に任命され以後満5年務める。 |
| 1944年(昭和19)8月8日 | 平隱村天川神社昇格につき、崇敬者総代として宮崎前村長と共に感謝状並びに記念品料を贈られる。 |
| 1946年(昭和21)4月15日 | 古稀賀会を平隱学校において開き、講演会・所蔵書画展を開催。賀筵をよろずやで行なう。 |
| 1947年(昭和22)4月13日 | 22年余り定住した平隱村から瑞穂村に帰る。 |
| 1947年(昭和22)11月 | 県恩給受給者連盟(退職公務員連盟)理事長となり恩給増額に尽力する。 |
| 1948年(昭和23)1月 | 信濃宮神社建設資金募集に奔走する。 |
| 1948年(昭和23)2月 | 全国恩給増額期成同盟(日本退職公務員連盟)会常任理事として恩給増額に尽力する。 |
| 1950年(昭和25)4月25日 | 三沢会長の案内にて倉田宮司宅一泊・翌大河原丸山旅館一泊・翌28日信濃宮例祭に参列、前島副会長宅宿泊・29日帰宅する。 |
| 1950年(昭和25)8月26日 | 恩給連盟代表として松原前会長、野本会長、斉藤副会長、大分県理事長等と会談する。 |
| 1950年(昭和25)11月29日 | 日本退公連特別委員会出席・翌30日常任理事会出席・12月1日全国代表者会出席・4日県常任理事会出席等退公連の活動に奔走する。 |
| 1951年(昭和26)4月 | 長野師範学校卒業生代表として信州大学教育学部記念図書館の寄付募集にあたる。 |
| 1952年(昭和27)6月 | 信濃史料集成購読賛成者を募り下高井・下水内郡下をまわる。 |
| 1952年(昭和27)10月 | 象山会々員募集にあたる。 |
| 1954年(昭和29)3月18日 | 日本退職公務員連盟常任理事を辞任し、参与となる。 |
| 県退職公務員連盟会長を辞任する。 | |
| 1954年(昭和29)5月 | 信濃宮維持資金募集にあたる。 |
| 1956年(昭和31)8月 | 岩菅山第28回の登山をする。最後の登山となる。 |
| 1959年(昭和34)11月26日 | 生家にて感冒に罹患、肺炎の併発により病死。戒名:慈光院釈藤山居士。 |
参考文献
| 堀金村誌 | 堀金村誌編纂委員会・堀金村公民館/編 | 安曇野市立図書館 |
|---|---|---|
| 佐藤藤山追憶集 | 編集者/佐藤春夫 | 信濃教育出版部 |





















