山田 実|安曇野ゆかりの先人たち
記事ID:0052242 印刷用ページを表示する 掲載日:2025年1月27日更新
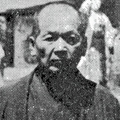
山田 実
やまだ みのる
農業の傍ら郷土文化の顕彰に大きく貢献。
| 生年月日 | 1882年(明治15) |
|---|---|
| 没年月日 | 1961年(昭和36) |
| 関連地域 | 穂高(上原) |
| 職業・肩書 | 氏子総代 |
| 活躍年 | 昭和時代 |
| ゆかりの分野 | 文化(学術思想) |
経歴
穂高上原に生れました。穂高小学校を卒業後、智学院に入塾し、美村飯島操に漢学を学びました。家業の農耕に精魂を傾け、上原の自然を友として自学自習し、想像力に富み、芸術味豊かな風韻気格(ふういんきかく)が形成されました。1904年(明治37)、中国東北で衛生兵として従軍しました。帰還後、烏川用水担当人に選ばれ、以来40年間名担当人として務めました。1907年(明治40)、穂高神社氏子総代に選ばれ、社格昇進に40年間尽力し、「穂高神社お舟飾り」に山田流の型を創出しました。また、忠魂碑奉安殿・画人明花の碑・一口付創始者喜悦宗匠の碑等の設計に携わったほか、栗尾山満願寺観音堂壁額・両部曼陀羅(まんだら)の復元、満願寺檀徒総代でも功績を残しました。穂高町会議員、南安曇郡誌編纂委員等の要職も勤めました。
略歴譜
| 1882年(明治15) | 穂高上原に生れる。 |
|---|---|
| 穂高小学校を卒業する。 | |
| 智学院に入塾し、美村飯島操に漢学を学ぶ。 | |
| 家業の農耕に精魂を傾け、上原の自然を友として自学自習し、想像力に富み、芸術味豊かな風韻気格が形成される。 | |
| 1904年(明治37) | 中国東北で衛生兵として従軍する。 |
| 帰還後、烏川用水担当人に選ばれ、以来40年間名担当人を務める。 | |
| 1907年(明治40) | 穂高神社氏子総代に選ばれ、社格昇進に40年間尽力し、「穂高神社お舟飾り」に山田流の型を創出した。 |
| 忠魂碑奉安殿・画人明花の碑・一口付創始者喜悦宗匠の碑等の設計に携わる。 | |
| 栗尾山満願寺観音堂壁額・両部曼陀羅の復元、満願寺檀徒総代でも功績を残す。 | |
| 穂高町会議員、南安曇郡誌編纂委員等を勤める。 | |
| 1961年(昭和36) | 亡くなる。 |
参考文献
| 南安曇郡誌第三巻下 | 南安曇郡誌改訂編纂会/編 | 安曇野市立図書館 |
|---|





















