小林 喜作|安曇野ゆかりの先人たち
記事ID:0027007 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月10日更新
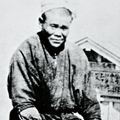
小林 喜作
こばやし きさく
北アルプスの名猟師。山案内人。槍ヶ岳登山の普及に尽力。
| 生年月日 | 1875年(明治8) |
|---|---|
| 没年月日 | 1923年(大正12) |
| 関連地域 | 穂高(牧) |
| 職業・肩書 | 北アルプスの名猟師・山案内人。 |
| 活躍年 | 明治時代 |
| ゆかりの分野 | 社会(社会事業) |
経歴
穂高牧に生れました。17歳で猟を始めたと言われています。この年、同郷の先輩、為右衛門老の案内で、槍ヶ岳の頂上に初めて立った後、猟のため北アルプス一帯を歩き回り、山道に精通しました。地図作製の為の測量官を奥地に案内して、測量にも参加しました。その後、多くの著名人の案内をし、登頂を成功へと導きました。当時、中房温泉を起点とした槍ヶ岳への縦走路は、4日も5日もかかっていました。当時の中房温泉経営者の百瀬彦一郎の依頼を受けた喜作は、猟でよく知っている、大天井から分岐して、赤岩岳・西岳を経て水俣乗越に下り、そこから東鎌尾根を登って、たった1日で楽に行ける新登山路の開拓に尽力しました。後にこの道は、「喜作新道」とも呼ばれ、多くの登山者に親しまれています。
略歴譜
| 1875年(明治8) | 0歳 | 穂高牧に生れる。 |
|---|---|---|
| 地図作製の為の測量官を奥地に案内し、測量にも参加した。槍ヶ岳に、60キロある三角点標石(御影石)を背負い上げた。 | ||
| 1912年(大正1) | 植物学者辻村伊助を、常念から餓鬼岳へ案内する。 | |
| 1918(大正7)から1922年(大正11) | 長男一男と「喜作新道」の開拓に携わる。松方三郎は、喜作があたかも銀座あたりを気楽に歩くように歩いたことから、「アルプス銀座」と名付けた。 | |
| 1922年(大正11)3月 | 積雪期に、槇有恒・松方三郎・大島亮吉等の槍ヶ岳初登頂を案内し、成功させた。 | |
| 1923年(大正12) | 出猟中、鹿島槍ヶ岳棒小屋沢で、長男一男と共に雪崩により亡くなる。 | |
| 1960年(昭和35) | 大天井岳の岩盤に、小川大系の作によるレリーフが設置された。 |
参考文献
| 長野県歴史人物大辞典 | 郷土出版/発行 | 安曇野市立図書館 |
|---|---|---|
| 山本茂実全集 第三巻 喜作新道 | 郷土出版/発行 | 安曇野市立図書館 |
| 写真:思い出のアルバム安曇 | 郷土出版/発行 | 安曇野市立図書館 |
| 梅干野成央ら 中房温泉の経営者による戦前期の山小屋建設とその立地計画 | 日本建築学会計画系論文集 | 第77巻第681号 |





















