松岡 弘|安曇野ゆかりの先人たち
記事ID:0052200 印刷用ページを表示する 掲載日:2025年1月27日更新
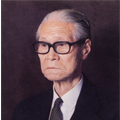
松岡 弘
まつおか ひろむ
激動の教育社会にあって70年、教育的信念を貫き通した教育者。
| 生年月日 | 1890年(明治23)12月19日 |
|---|---|
| 没年月日 | 1983年(昭和58)3月8日 |
| 関連地域 | 三郷(下長尾) |
| 職業・肩書 | 教育功労者 |
| 活躍年 | 昭和時代 |
| ゆかりの分野 | 文化(教育) |
経歴
三郷下長尾に生れました。梓農業補習学校頃から教師を志し、1908年(明治41)、長野県師範学校(現信州大学教育学部)に入学しました。在学中に手塚縫蔵と出会い、やがて聖書を信仰の書とし、22歳で洗礼を受けました。1912年(明治45)、師範学校を卒業し、訓導・校長・県視学官として活躍しました。温明騒動、星菊太師範学校長の辞職勧告、敗戦時の自主的な人事の刷新と辞表提出等、教育的信念を貫きました。1948年(昭和23)、日本教育会総会で、教育会・教員組合一本論に反対しましたが否決され、翌年、日本教育協会(今日の日本連合教育会)を結成しました。1954年(昭和29)、東京において、教員の政治活動制限法案に反対する集会を開きました。信濃教育会長を、1956年(昭和31)から1978年(昭和53)まで、日本連合教育会会長を、1975年(昭和50)から1983年(昭和58)まで勤めました。1983年(昭和58)3月8日、92歳で亡くなりました。
略歴譜
| 1890年(明治23)12月19日 | 三郷下長尾に生れる。 |
|---|---|
| 1904年(明治37) | 梓・倭村組合立高等小学校に併設する梓農業補習学校に入学し、小学校から同級の務台理作と共に通学する。このころから教師を志望するようになる。 |
| 1906年(明治39) | 家人にようやく許されて、5月から松本にある師範学校進学予備校の私立教育学校に徒歩で通う。11月、学校をやめ、家で勉強する。師範学校入学予備試験に合格、本試験は不合格となったが、再度受験して合格する。 |
| 1908年(明治41) | 長野県師範学校に入学する。4年生の時、後町小学校教務主任手塚縫蔵宅を訪問、読み込んである聖書をみて衝撃を受け、修養の書として読み始める。 |
| 1912年(明治45) | 長野県師範学校を卒業する。南安曇郡温明小学校訓導となる。岡村千馬太を主とする「東西南北会」に出席、小原福治を知る。校長と職員が対立した、いわゆる温明騒動のリーダーと見られ、1年にして転出する。 |
| 1913年(大正2) | 西筑摩郡三尾小学校訓導となる。読書思索に集注し、聖書を信仰の書として読むようになり、洗礼を受ける。 |
| 1914年(大正3) | 諏訪郡玉川小学校訓導となる(校長手塚縫蔵)。 |
| 1915年(大正4) | 本県師範学校改革に関して協議、代表12名の一人として、星菊太師範学校長の辞職勧告を行い、休職を命ぜられる。夏、軽井沢での東京富士見町教会の夏季講習に手塚縫蔵と出席、植村正久そのほかに会う。 |
| 1916年(大正5)から 1925年(大正14) |
1916年(大正5)、倭小学校訓導となる。1919年(大正8)に、後町小学校訓導となり、1922年(大正11)、倭小学校長となる。 |
| 1925年(大正14) | 「信濃教育」3月号に、川井訓導の修身教授問題につき寄稿し、児童への専念こそが教育者の生命であると論じ、教科書使用の有無の如き表面的事象による処罰を難ずる。 |
| 1926年(大正15) | 穂高小学校長に就任する。水曜日の夜は、井口喜源治宅での祈祷会、日曜日には、松本教会の礼拝に参加する。 |
| 1931年(昭和6)から 1933年(昭和8) |
長野県視学となる。御真影盗難事件、二・四事件、大不況下の教員給の寄附や支払い延滞等に当面する。 |
| 1934年(昭和9) | 北佐久郡小諸尋常高等小学校長となる。多彩な職員組織によって「梅花教育」を進める。 |
| 1939年(昭和14) | 長野県派遣満鮮教育視察団員として、一か月間務める。 |
| 1940年(昭和15) | 宿泊教育施設「竹原寮」を設置する。 |
| 1945年(昭和20) | 長野県地方視学官となる。県教育行政府の首席視学官として、国家主義教育をしてきた責任を明らかにする意味で、自主的に人事の刷新を図り、自らも辞表を提出する。 |
| 1946年(昭和21) | 大日本教育会長野県支部事務局長に就任する。小諸町立小諸中学校(旧制)名誉校長を1949年(昭和24)まで勤める。支部を解散し独立して信濃教育会に復元する。 |
| 1947年(昭和22) | 信濃教育会副会長となり、信濃教育会内に教育研究所を創設する。信濃教育会出版部門を独立させ社長に就任する。 |
| 1948年(昭和23) | 日本教育会総会で、解散に強行に反対(教員会・教員組合一本論)するが、否決される。直後、数府県の代表と共に日本教育協会(今日の日本連合教育会)の結成を約す。 |
| 1949年(昭和24) | 日本教育協会発会式が行なわれ、常任理事となる。 |
| 1951年(昭和26) | 信濃教育会最初の代表として、Wotp(今日のWcotp)第5回マルタ島会議に出席する。 |
| 1954年(昭和29) | 2月21日、「教員の政治活動制限法案反対東京大会」を台東区下谷小学校に開催、続いて衆参両院議長に請願、文相に陳情する。長野県退職公務員連盟会長となり、1982(昭和57)まで勤め、小学校国語・理科教科書を発行する。 |
| 1956年(昭和31)から 1978年(昭和53) |
信濃教育会長を勤める。 |
| 1963年(昭和38) | 日本退職公務員連盟副会長となる。 |
| 1975年(昭和50)から 1983年(昭和58) |
日本連合教育会会長を勤める。 |
| 1983年(昭和58)3月8日 | 亡くなる。 |
参考文献
| 穂高町誌 | 穂高町誌編纂委員会/編 | 安曇野市図書館 |
|---|---|---|
| 師道 | 松岡弘先生講述集刊行会/編 | 安曇野市図書館 |





















