清沢 清志|安曇野ゆかりの先人たち
記事ID:0052212 印刷用ページを表示する 掲載日:2025年1月27日更新
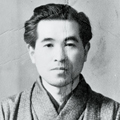
清沢 清志
きよさわ きよし
演劇家。吉行エイスケらと新興芸術運動をすると共に、自宅を人々に開放し、「安曇野モダニズム」の拠点として大きな影響を与えた。
| 生年月日 | 1905年(明治38) |
|---|---|
| 没年月日 | 1959年(昭和34) |
| 関連地域 | 穂高(神田町) |
| 職業・肩書 | 文芸家・演劇家 |
| 活躍年 | 昭和時代 |
| ゆかりの分野 | 文化(文芸) |
経歴
穂高神田町に生まれました。1921年(大正10)12月、自宅の製糸工場の寄宿舎で、金子洋文作「老船夫」と農民一揆を舞台化したアイルランドの翻訳劇一幕を上演、穂高演劇協会の幕開けとなりました。演劇協会発足以来の上演脚本250本、公演は県下各地500回に達しました。1925年(大正14)、友人らとモダニズムの先駆的雑誌「売恥醜文」を発行しました。1929年(昭和4)には、松本の劇団青服劇場に協力して、建国座でルメルテンの「坑夫」他を上演しました。また、劇団向日葵座と共演し、松竹座で公演を持ちました。1930年(昭和5)に、第二次信州詩人連盟講演会を行いました。1932年(昭和7)には、清沢宅にて、「すうぶにいるの会」が発足されました。終戦後は、松本平や伊那谷等で、積極的に移動公演に取り組みました。
略歴譜
| 1905年(明治38) | 穂高神田町に生まれる。 |
|---|---|
| 1921年(大正10)12月 | 金子洋文作「老船夫」と農民一揆を舞台化したアイルランドの翻訳劇一幕を上演、穂高演劇協会の幕開けとなる。 |
| 1925年(大正14) | 友人等とモダニズムの先駆的雑誌「売恥醜文」を発行する。 |
| 1929年(昭和4) | 松本の劇団青服劇場に協力して、建国座でルメルテンの「坑夫」他を上演する。 |
| 劇団向日葵座と共演し、松竹座で公演を持つ。 | |
| 1930年(昭和5) | 第二次信州詩人連盟講演会を行う。 |
| 1932年(昭和7) | 清沢宅にて、「すうぶにいるの会」が発足される。 |
| 1933年(昭和8)6月 | 町内同好の人々と同人雑誌「草塔」を発行する。 |
| 1933年(昭和8) | 同人雑誌「草塔」のメンバーによる「藤村会」をつくり、郷土文芸の振興に貢献する。 |
| 終戦後、松本平や伊那谷等で、積極的に移動公演に取り組む。 | |
| 1952年(昭和27) | 夏期の自主公演と秋の穂高町文化祭の年2回発表する。 |
| 1959年(昭和34) | 死去。 |
参考文献
| 穂高町誌 | 穂高町誌編纂委員会/編 | 安曇野市図書館 |
|---|---|---|
| 安曇野の美術 | 丸山楽雲/編 | 安曇野市図書館 |
| 写真:穂高町誌 | 穂高町誌編纂委員会/編(原板) |





















