藤森 寿平|安曇野ゆかりの先人たち
記事ID:0052040 印刷用ページを表示する 掲載日:2025年1月27日更新
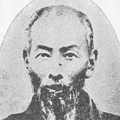
藤森 寿平
ふじもり じゅへい
法蔵寺で実践社、武居用拙塾を興し、南安曇郡の近代教育の先駆。長野県国会開設運動の推進。日本画家。
| 生年月日 | 1835年(天保6)10月6日 |
|---|---|
| 没年月日 | 1905年(明治38)7月26日 |
| 関連地域 | 豊科(新田) |
| 職業・肩書 | 教育功労者・日本画家 |
| 活躍年 | 明治時代 |
| ゆかりの分野 | 文化(教育) |
経歴
豊科新田に生れました。藤森一族の学問所で寺所の細萱伝平から読み書きを教えられました。長じて漢学は三郷中萱の相馬古処、和歌は歌人丸山保秀の教えを受けました。1854年(安政1)に松本に来た南宗画家古曳盤谷に入門しました。盤谷は佐久間象山とも親交を持っていました。24歳で勤皇討幕の策源地京都へ行き、儒者山中静逸に入門しました。絵画は南宗画家村山半牧、和歌を当時の桂園派歌人香川景恒に学びました。1870年(明治3)、同志とはかって松本藩の知事に学校設置の提言書を出しました。翌年、自費を投じて法蔵寺境内に学塾を設け、高遠藩士高橋白山、菁我館師範武居用拙等を招いて人材育成を行いました。1879年(明治12)、国会開設請願運動のための結社「奨匡社」の運動に携わりました。1880年(明治13)、県会議員となり、日当増額に反対して政界を去りました。1883年(明治16)に北安曇郡北山学校長、1886年(明治19)に小倉学校長となりました。母親の死去に伴い、画家一途の道を歩み、遊歴が10回以上に及びました。1905年(明治38)、浅草の寺院にて、制作中に亡くなりました。
略歴譜
| 1835年(天保6)10月6日 | 豊科新田の藤森郁三郎の長男に生れる。名を厚、長じて寿平という。桂谷は主たる号。 |
|---|---|
| 藤森一族の学問所であった。寺所の細萱伝平から読み書きを教えられる。 | |
| 長じて漢学は三郷中萱の相馬古処、和歌は歌人丸山保秀の教えを受ける。 | |
| 1854年(安政1) | 松本に来た南宗画家古曳盤谷に入門する。盤谷は佐久間象山とも親交も持っていた。 |
| 勤皇討幕の策源地京都へ行き、儒者山中静逸に入門する。絵画は南宗画家村山半牧、和歌を当時の桂園派歌人香川景恒に学ぶ。 | |
| 1870年(明治3) | 同志とはかって松本藩の知事に学校設置の提言書を出す。 |
| 1871年(明治4) | 自費を投じて法蔵寺境内に学塾を設け、高遠藩士高橋白山、菁我館師範武居用拙等を招いて人材育成を行う。 |
| 1879年(明治12)9月 | 豊科村第1回の村会で副議長を務める。 |
| 1879年(明治12) | 国会開設請願運動のための結社「奨匡社」の運動に携わる。 |
| 1880年(明治13) | 県会議員となる。「藤森桂谷の味噌なめ演説」が新聞記事で有名となり、日当増額に反対して政界を去る。 |
| 1883年(明治16) | 北安曇郡北山小学校長となる。 |
| 1886年(明治19) | 小倉小学校長となる。 |
| 母親の死去に伴い教育界を去り、画家一途の道を歩む。越後・関東・東北等を、2か月から2か年の遊歴が10回以上に及ぶ。 | |
| 1903年(明治36) | 再び上京して、画道の修習に努める。 |
| 1905年(明治38)7月26日 | 浅草の寺院にて、制作中に亡くなる。 |
参考文献
| 南安曇郡誌第三巻下 | 南安曇郡誌改訂編纂会/編 | 安曇野市図書館 |
|---|---|---|
| 豊科町誌 | 豊科町誌編纂会/編 | 安曇野市図書館 |
| 藤森桂谷の生涯 | 南安曇教育会/編 | 安曇野市図書館 |
| 夜明けの鐘 桂谷 藤森寿平小伝 | 中野 正實/著 | 安曇野市図書館 |





















