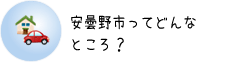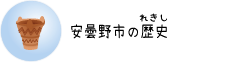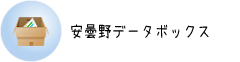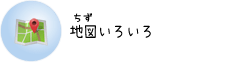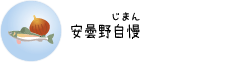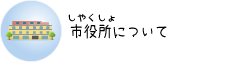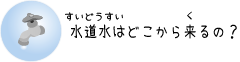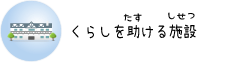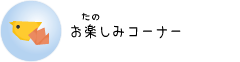ニジマス・しんしゅうサーモン
記事ID:0002409 印刷用ページを表示する 掲載日:2015年10月29日更新

信州サーモンの、より分け作業
あづみの市は、全国でも指おりのニジマスの産地(さんち)です。わき水がほうふな川ぞいなどに、ニジマスを育てる池 “養鱒池(ようそんち)” が数多くあります。
近ごろは、ニジマスとブラウントラウトという魚を合わせて生まれた “しんしゅうサーモン” が注目を集めています。
しんしゅうサーモンは、ニジマスとくらべてなめらかで身もあつく、うま味が多いのがとくちょうです。しんしゅうサーモンのたまごは、あづみのでしか作れません。あづみのを代表する特産品(とくさんひん)となることが、きたいされています。
ニジマス養殖(ようしょく)のはじまり
むかしは、あづみのの川でも、サケやマスをとることができました。たまごを生むために、海から川をのぼって泳いできていたからです。そのころは、サケやマスをとることを仕事にしている人も多くいました。
しかし、水力発電所やダムが作られるようになると、海の魚はあづみのまで来ることができなくなってしまいました。そこで考えついたのが、当時日本ではじまったばかりのニジマスの養殖(ようしょく)でした。わき水がほうふなあづみのは、自分たちでニジマスを育てる“養殖”を行うのに、とても良い場所だったのです。
大正15年、あかしなの倉科多策(くらしな・たさく)という人が、マスの養殖場(ようしょくじょう)を作りました。これが今の「長野県水産試験場(ながのけん すいさん しけんじょう)」となりました。おかげで、ニジマス養殖がますますさかんになり、しんしゅうサーモンを生みだすなど、あづみのの水産業のはってんにつながりました。