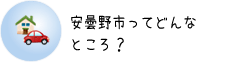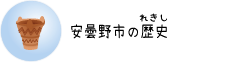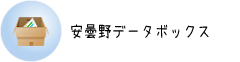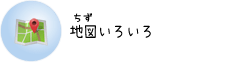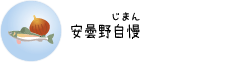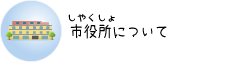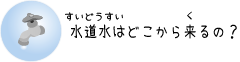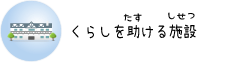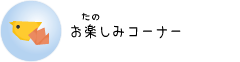田園産業都市(でんえんさんぎょうとし)をめざして
記事ID:0002428 印刷用ページを表示する 掲載日:2015年10月29日更新
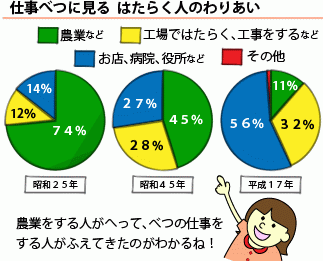
昭和(しょうわ)に入ると、それまで農業がおもな産業(さんぎょう)だった安曇野(あづみの)に、最先端(さいせんたん)の技術(ぎじゅつ)をもつ工場ができはじめます。
豊科町のころのデータをみると、昭和35年に57だった工場の数も、昭和40年には73にふえました。そこではたらく人の数も、1838人から4345人とおよそ2.4倍もふえました。
また昭和40年代ごろになると、そこではたらく人たちなどのために多くの団地ができはじめます。昭和20年代なかばから少しずつへっていた人口も、このころからどんどんふえてきました。

観光客でにぎわう穂高駅(昭和60年ごろ)
観光地(かんこうち)としての安曇野が花開くのも、ちょうどこのころです。昭和47年、穂高山ろくの旅館(りょかん)や施設(しせつ)へ温泉(おんせん)がひかれ、温泉地「穂高温泉郷(ほたかおんせんきょう)」ができました。それまでも北アルプス登山の出発点として、たくさんの人がおとずれていた安曇野ですが、これをきっかけに観光地としての発展(はってん)にはずみがつきました。
いまでは温泉や登山だけでなく、トレッキングや美じゅつ館めぐり、おそばなどおいしいものを楽しみに、年間100万人ほどの人が安曇野をおとずれています。
そして平成(へいせい)をむかえ、全国で町や村の合併(がっぺい)がすすめられるなか、平成17年10月、豊科町・穂高町・三郷村・堀金村・明科町が合併し「安曇野市」が誕生しました。
これからも、人びとのくふうで発展してきた産業とめぐまれた自然を守り育て、みんなが幸せにくらせる市をめざして、安曇野市は歴史(れきし)を重ねていきます。
- 「仕事べつに見るはたらく人のわりあい」のグラフ…昭和25年・45年データについては南安曇郡誌 三巻(上)を、平成17年データについては国勢調査の結果を参考にしました。
- 観光客の数は、平成17年から21年における碌山美術館・わさび園周辺の利用者数より。(資料:長野県観光地利用者統計調査結果)