本文
令和4年度安曇野市文書館前期企画展「安曇野の災害ー先人は何を考え、どう動いたかー」
企画展「安曇野の災害ー先人は何を考え、どう動いたかー」
開催日時 令和4年5月8日日曜日から令和4年8月31日水曜日まで
会 場 安曇野市文書館1階閲覧コーナー
主 催 安曇野市教育委員会
担 当 安曇野市教育委員会教育部文化課博物館担当(安曇野市文書館)
直下に活断層があり、犀川をはじめとして大小様々な河川や水路を持つ安曇野には、過去多くの災害の歴史があります。南安曇郡誌、旧5町村の自治体誌、消防協会周年誌、消防団誌、信濃毎日新聞、安曇野市HP等によれば明治以降の災害(民家火事を除く)の約8割は、水害でした。今回の企画展では、文書館に収蔵されている資料の展示や講演会、講座をもとに安曇野の地形や地質の持つ特性や災害や防災と向き合ってきた先人の姿を紹介します。危機管理課や消防団、各地区の自主防災組織の防災・減災に向けた取組により、火災や水害の発生件数は減少しています。災害という視点で安曇野への理解を広げることができます。

1.災害の記録、傷跡
震災
安曇野は、フォッサマグナ(大地溝帯)上に位置しています。南海トラフと同様に大きな地震がいつ起きてもおかしくない状況ですが、過去に人的被害(死亡)が記録された資料はまだ見つかっていません。
大正7(1918)年11月11日に発生した大町地震では、余震が3日後の14日まで続いています。当時、スペイン風邪が猛威を振るう中で、震災が重なっていました。
火災
南安曇郡誌や旧5町村の自治体誌によると、明治以降大火として記録されている火災は、10件です。大正8(1919)年3月16日に発生した有明村大火では、消火用水も少なく道も工事でポンプ車が入ることができなかったため大きな被害になりました。
しかし、年代とともに火災が減少しています。暖房や調理などの家庭設備の変化がその要因のひとつとして考えられるのかもしれません。
水害
民家火災を除くと安曇野の災害はその8割が水害です。近年では、令和3年8月15日に犀川の増水により、明科地域に避難指示が出されています。
しかし、その水害の発生件数も年代とともに減少しています。広域排水事業所新設や堤防、排水路の整備など防災、減災のための取組の成果と考えられます。
2.旧5町村防災のあゆみ
明治以前は、地域の消火は自分たちの責任において執り行うという考え方でした。現代の自助、共助の考えに共通します。
昭和23(1948)年3月「消防組織法」が施行され、自治体による消防機関がスタートします。
昭和36(1961)年には「災害対策基本法」が制定されます。この基本法は、その後改定を重ね、現在につながっています。
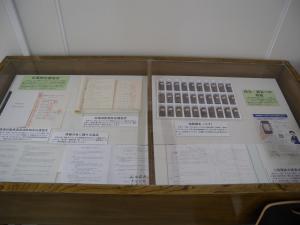
3.安曇野市防災のあゆみ
安曇野市では、災害に備えて様々は団体や企業と協定を結んできました。
災害に関わる情報伝達充実のための取り組みとして、平成23年(2011)年10月に「デジタル移動系防災無線システム」が開局しました。
平成26(2014)年から、防災情報を配信する「安曇野市メール配信サービス」が運営されています。
4.防災、減災の環境づくり
安曇野市が平成19(2007)年3月に策定した『安曇野市地域防災計画』では、「災害に強い地域づくり」として、「災害警戒地の改修や防災施設の新設」「市民の防災力の向上と人的ネットワークづくり」「多くの団体や企業との連携」「災害に関する情報伝達力の充実」を挙げています。
そのうちの一つとして、非常備の消防機関として消防団があります。団員は、各自の職に就きながら平時の防災活動や災害時の救援活動に従事する組織です。

関連講演会・講座
*下記の講演会・講座は終了しました。
文書館で配布資料や記録DVDをご覧いただけます。
講座「われらが安曇野市消防団」
火災・水害は、いつの時代であっても平穏な市民の生活を揺るがす災害です。
その最前線に立って、市民の身体や財産を守るために活動している消防団のあゆみについて文書館資料を通して学びます。
日 時 令和4年5月22日日曜日 午後1時30分から午後3時まで
講 師 平沢 重人(文書館長)
*文書館に記録DVDがあります。
講座「古文書から読み解く善光寺地震」
三郷務台家文書「公私年々雑事記」には、弘化4年(1847)年善光寺地震のことが記録されています。古文書を通して、善光寺地震を読み解きます。
日 時 令和4年7月17日日曜日 午後1時30分から午後3時まで
講 師 赤羽根 嘉矩 氏(三郷郷土研究会)
講演会「活断層と地震がつくった安曇野」
科学的な視点での安曇野の地形や地質の特性、被災の実態について豊富な資料をもとに解説します。
日 時 令和4年6月26日日曜日 午後1時30分から午後3時まで
講 師 大塚 勉 氏(信州大学名誉教授)
*文書館に記録DVDがあります。
*『安曇野市文書館紀要第4号』に講演記録を掲載しています。



